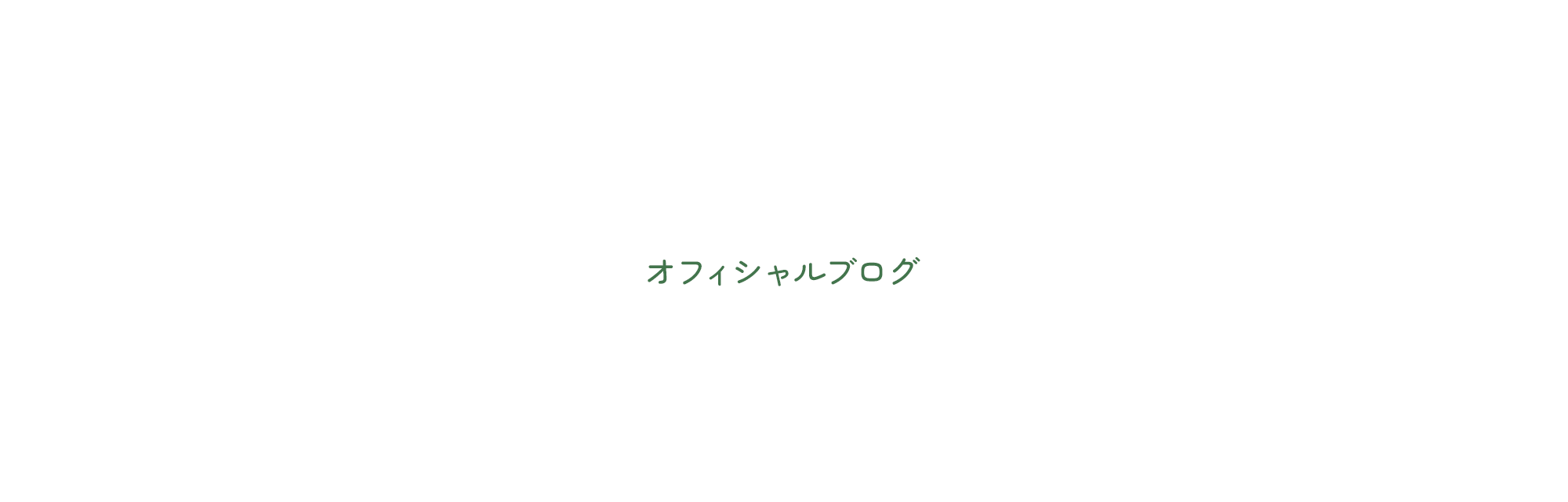
第4回ニラ雑学講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第4回ニラ雑学講座!
今回は、ニラを使った美味しいレシピについてです
ニラは炒め物やスープ、餃子の具材としておなじみですが、他にも美味しく食べられるレシピがたくさんあります。
今回は、家庭で簡単に作れる人気のニラ料理をいくつかご紹介します。
1. 定番!ニラの卵とじ
シンプルで栄養満点! 朝ごはんやお弁当のおかずにもぴったりです。
材料(2人分)
ニラ … 1束
卵 … 2個
しょうゆ … 大さじ1
みりん … 大さじ1
だし … 100ml
作り方
ニラを4~5cmの長さにカットする。
フライパンにだし、しょうゆ、みりんを入れて火にかける。
煮立ったらニラを加え、溶き卵を流し入れる。
弱火でふんわり火を通し、完成。
2. ニラたっぷり餃子
材料(20個分)
ニラ … 1束
豚ひき肉 … 200g
キャベツ … 100g
餃子の皮 … 20枚
しょうが・にんにく(すりおろし) … 各小さじ1
塩・こしょう … 少々
ごま油 … 大さじ1
作り方
ニラとキャベツを細かく刻む。
ボウルにひき肉、野菜、調味料を入れてよく混ぜる。
餃子の皮に包み、焼く or 茹でて完成。
3. ニラのチヂミ
材料(2~3人分)
ニラ … 1束
小麦粉 … 100g
片栗粉 … 50g
卵 … 1個
水 … 100ml
塩 … 小さじ1/2
ごま油 … 大さじ1
作り方
ニラを5cmの長さに切る。
ボウルに小麦粉、片栗粉、卵、水、塩を入れて混ぜる。
ニラを加えてさらに混ぜる。
フライパンにごま油を熱し、両面をカリッと焼く。
4. まとめ
ニラの卵とじで手軽に栄養補給!
餃子やチヂミでボリュームたっぷりの食事に!
ニラの香りと風味を活かした料理で、毎日の食卓を彩ろう!
次回は「ニラ農園のこだわり~美味しいニラを育てる秘訣」についてご紹介します。お楽しみに!
以上、第4回ニラ雑学講座でした!
次回の第5回もお楽しみに!
![]()
第3回ニラ雑学講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第3回ニラ雑学講座!
今回は、美味しいニラの見分け方と選び方についてです
ニラは一年中手に入る便利な野菜ですが、せっかくなら新鮮で美味しいものを選びたいですよね。
今回は、美味しいニラを見分けるコツや、スーパーや市場で購入する際の選び方のポイントをご紹介します。
さらに、買った後の保存方法や、鮮度を保つ秘訣についても解説します。
1. 美味しいニラの特徴
新鮮なニラを見分けるポイントは**「色・香り・葉の状態」**の3つです。
鮮やかな緑色をしているか → くすんだ色や黄色っぽいものは避ける。
香りがしっかりしているか → ニラ特有の香りが強いものが新鮮。
葉がピンと張っているか → しおれているものや先端が枯れているものはNG。
また、茎の部分が細すぎるものは柔らかいが、太すぎると筋が多くなるため、程よい太さのものを選ぶと食感も良くなります。
2. スーパーや市場での選び方
スーパーでニラを選ぶときは、以下のポイントをチェックしましょう。
パック入りのもの: 水分がしっかり保たれているか確認。乾燥していないものを選ぶ。
束で売られているもの: 根元がしっかりしており、葉が倒れていないかをチェック。
産地の確認: 旬の時期(春・秋)は地元産のものを選ぶと鮮度が良い。
市場や直売所では、生産者の名前が記載されているものが新鮮なことが多く、直接農家の人に聞いて選ぶのもおすすめです。
3. ニラの保存方法と鮮度を保つコツ
ニラは傷みやすいため、適切な方法で保存することが大切です。
冷蔵保存(短期間の場合)
使いかけのニラは濡らしたキッチンペーパーに包み、ビニール袋に入れて野菜室へ。
保存期間: 3~4日程度。
冷凍保存(長期間の場合)
使いやすい長さにカットし、ジップロックに入れて冷凍庫へ。
保存期間: 約1ヶ月。
ポイント: 凍ったまま料理に使えるので便利。
水に浸けて保存(鮮度維持)
コップに水を入れて、ニラの根元を浸けると、冷蔵庫で約1週間持つ。
水は2日に1回交換すると、より長持ちする。
4. まとめ
美味しいニラを選ぶには、色・香り・葉の状態をよく観察することがポイントです。
鮮やかな緑色で香りが強いものを選ぶ。
スーパーでは水分がしっかり残っているものをチェック。
冷蔵や冷凍保存を使い分けると長持ちする。
次回は「ニラを使った美味しいレシピ」をご紹介します。
毎日の食卓に取り入れやすい、簡単で美味しいニラ料理をたくさん紹介しますので、お楽しみに!
以上、第3回ニラ雑学講座でした!
次回の第4回もお楽しみに!
![]()
第2回ニラ雑学講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第2回ニラ雑学講座!
今回は、ニラ農園の一年についてです
前回はニラの基本的な栽培についてお話ししました。
今回は、ニラ農園の一年間の流れについてご紹介します。
ニラは長期間収穫できる作物ですが、季節ごとに適切な管理を行うことが、美味しいニラを育てる秘訣です。
各季節ごとの作業を詳しく解説していきます。
1. 春(3月~5月)~植え付けと成長管理~
春はニラの植え付けと新芽の成長が始まる大切な時期です。
寒さが和らぎ、気温が上昇するこの季節は、苗の定着や根の発達に最適です。
種まきと苗の植え付け
3月頃から温暖な気候を利用し、畑に種をまいたり、苗を植え付けたりします。
種まきから始める場合は発芽に時間がかかるため、ポット苗を育ててから植える方法もあります。
土の管理
栄養たっぷりの土壌を維持するため、有機肥料を追加します。
特に腐葉土や堆肥をしっかり混ぜ込むことで、根の成長を助けます。
雑草取りと間引き
成長を妨げる雑草をこまめに除去します。
また、密集しすぎたニラを間引くことで、日光や風通しを良くし、病害の予防にもつながります。
初期の水やり
苗が根付くまでは適度に水を与え、乾燥を防ぎます。
ただし、過剰な水やりは根腐れの原因となるため、排水性を確保することも重要です。
2. 夏(6月~8月)~収穫と水管理~
夏はニラの成長が最も活発になり、収穫の最盛期を迎えます。
この時期の管理が収穫量や品質に大きく影響します。
水やり
夏の強い日差しで土が乾燥しやすいため、朝と夕方の2回水やりを行い、適度な湿度を維持します。
特に猛暑の日は、葉焼けを防ぐために日除けを設置することも有効です。
病害虫対策
夏場は害虫が発生しやすく、アブラムシやハダニがニラに付着すると生育が悪くなるため、防虫ネットや適切な農薬を使用します。
また、害虫が発生しやすい環境を防ぐために、風通しを良くし、湿度管理を徹底することも大切です。
収穫作業
ニラは刈り取った後、約1ヶ月で次の収穫が可能となります。
刈り取る際は根元を2~3cmほど残すことで、新しい葉がスムーズに成長します。
追肥の実施
収穫が続くため、養分の補給も欠かせません。
窒素分の多い肥料を適量追加することで、次の収穫に向けてしっかりとした葉を育てることができます。
3. 秋(9月~11月)~栄養補給と冬支度~
秋は、ニラを冬越しさせるための準備をする時期です。
涼しくなり、病害虫の発生も減るため、土壌改良や株の強化に最適な季節です。
肥料の追加
根の成長を促し、冬の寒さに耐えられるようにするため、有機肥料や緩効性肥料を補充します。
特に、窒素系の肥料を適量施すことで、葉の厚みが増し、収穫量の向上につながります。
害虫駆除と病気予防
夏に残った害虫が秋にも影響を与えるため、収穫後の畑をしっかり観察し、必要に応じて防虫対策を継続します。
また、収穫後の不要な葉を除去することで、病害の発生を防ぐことができます。
適度な刈り込み
冬に向けて、ニラの生育を整えるために、適度に刈り取ります。
刈り込みすぎると冬の間に養分が不足してしまうため、バランスを見ながら管理することが重要です。
4. 冬(12月~2月)~休眠期と次のシーズンへの準備~
冬はニラの成長が止まり、休眠期に入りますが、この時期の管理が翌年の収穫に大きく影響します。
防寒対策
霜や寒風から守るため、ビニールトンネルやマルチシートを活用し、極端な冷え込みを防ぎます。
また、根が凍るのを防ぐために、敷き藁を利用して土の保温性を高める方法もあります。
土壌改良
冬の間に土を休ませるため、石灰をまいて酸度調整を行ったり、堆肥を混ぜ込んで微生物の働きを活性化させたりします。
次シーズンの計画作り
冬の間に、来年の収穫計画を立てたり、種の準備を進めたりすることが、効率的な農園運営につながります。
5. まとめ
ニラ農園の一年は、季節ごとに異なる管理が必要です。
それぞれの時期に適切な作業を行うことで、一年中安定した収穫を可能にします。
春: 植え付けと成長管理を徹底し、根をしっかり定着させる。
夏: 収穫の最盛期。水管理や害虫対策を徹底し、高品質なニラを育てる。
秋: 栄養補給を行い、冬に備えて株を強くする。
冬: 土壌改良と防寒対策を実施し、翌シーズンの準備を進める。
次回予告!
次回は「美味しいニラの見分け方と選び方」についてご紹介します。新鮮なニラを見極めるコツや、スーパーで購入する際のポイントを解説しますので、お楽しみに!
以上、第2回ニラ雑学講座でした!
次回の第3回もお楽しみに!
![]()
第1回ニラ雑学講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
いよいよ寒くなってきましたが、皆さん元気に過ごされていますか?
風邪をひかないよう、防寒対策を徹底していきましょう!
さて、本日からシリーズ更新が始まります!
山村農園監修!
ニラ雑学講座!
ニラに関する豆知識を毎回少しずつお届けしたいと思います。
記念すべき第1回目のテーマは!
ニラ農園についてです!
ニラは香りが豊かで、炒め物やスープ、餃子の具材としても人気の野菜です。
栄養価が高く、食卓で幅広く活用されることから、多くの農家が栽培に力を入れています。
ニラ農園では、どのようにして新鮮で美味しいニラが育てられているのでしょうか?
今回は、ニラの魅力と基本的な栽培の流れについて詳しくご紹介します。
1. ニラの魅力とは?
① 豊富な栄養価
ニラはビタミンA、C、E、鉄分、食物繊維が豊富に含まれており、健康維持に役立つ成分が多く含まれています。
特に、アリシンという成分が含まれているため、疲労回復や免疫力向上に効果的です。
疲労回復: ニラに含まれる「アリシン」が、体のエネルギー代謝をサポートし、疲れにくい体づくりを助ける。
免疫力向上: 抗酸化作用のあるビタミンCやEが、体の健康維持に役立つ。
腸内環境改善: 食物繊維が豊富で、腸の調子を整える効果が期待できる。
ニラは健康に良いだけでなく、美容にも効果的な成分が含まれており、肌の調子を整えたり、血行を促進したりする働きもあります。
② 長期間収穫できる野菜
ニラは多年草なので、一度植えれば何年も収穫を楽しめる野菜です。
適切に管理すれば、年に4〜5回ほど収穫が可能で、農家にとっても安定した収益が期待できる作物です。
一度植えれば何年も育つので、管理がしやすい
定期的に刈り取ることで、繰り返し収穫できる
寒さに強く、年間を通じて安定した栽培が可能
③ 料理に欠かせない万能食材
ニラは独特の風味があり、料理のアクセントとして重宝されます。
特に中華料理では欠かせない存在で、炒め物やスープ、餃子、チヂミなどに活用されています。
炒め物: ニラレバ炒め、ニラ玉炒めなど、香ばしい風味が楽しめる。
スープ: 味噌汁や中華スープに加えると、風味がアップ。
餃子: ニラとひき肉を合わせることで、旨味たっぷりの餃子に。
チヂミ: 韓国料理の定番、ニラたっぷりのもちもちチヂミ。
どんな料理にも馴染みやすく、食欲をそそる香りが魅力の野菜です。
2. ニラの栽培の基本
① 土作りと種まき
ニラは排水性がよく、日当たりの良い環境で育ちやすい野菜です。
栽培前に土壌をしっかり整えることが重要で、有機肥料や堆肥を混ぜ込んで栄養たっぷりの土壌を作ります。
水はけが良い土を作るために、畝を高めにする。
種まきのタイミングは春(3月〜4月)または秋(9月〜10月)が最適。
種をまいた後は適度な水やりを行い、発芽を促す。
② 水やりと管理
ニラは乾燥に強い一方で、根元が乾きすぎると生育が悪くなるため、適度な水やりが必要です。
また、雑草が生えやすいので、こまめに除草することで成長を促します。
発芽から定着するまでの期間は、水やりをしっかり行う。
土が乾燥しすぎないように、適度な湿度を保つ。
雑草が生い茂ると、養分が奪われるため、こまめに除草を行う。
ニラは比較的丈夫な野菜ですが、害虫対策も重要です。
特にアブラムシやハダニがつきやすいため、農薬を使わずに防虫ネットを活用する農家も増えています。
③ 収穫のタイミング
ニラの収穫は、葉の長さが30cm程度になったら行います。
収穫の際には、根元を2~3cmほど残して刈り取ることで、次の収穫に向けて新しい葉が育ちやすくなります。
収穫後はすぐに冷却し、鮮度を保つ。
刈り取るとすぐに新しい芽が出るため、1ヶ月後には再び収穫が可能。
適切なタイミングで刈り取ることで、品質の良いニラを維持できる。
ニラは刈り取るとどんどん新しい葉が伸びるため、年間を通じて安定した収穫が可能な作物です。
3. まとめ
ニラは、栄養価が高く、料理にも幅広く使える便利な野菜です。
農園での栽培は比較的管理がしやすく、長期間収穫できるため、農家にとっても魅力的な作物です。
健康維持に役立つ栄養素が豊富。
年に何度も収穫が可能で、栽培しやすい。
さまざまな料理に使える万能食材。
ニラは、家庭でも手軽に育てることができるため、家庭菜園にもおすすめの野菜です。
水はけの良い土と日当たりを確保すれば、初心者でも育てやすいのが特徴です。
次回予告!
次回は「ニラ農園の一年~季節ごとの管理と作業」について詳しく解説します。
ニラの成長に合わせた管理のポイントや、一年を通しての作業スケジュールをご紹介しますので、お楽しみに!
以上、第1回ニラ雑学講座でした!
次回の第2回もお楽しみに!
![]()
第6回野菜の魅力講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第6回野菜の魅力講座!
環境に優しい中国野菜の栽培と活用についてです。
家庭でできる持続可能な栽培方法
中国野菜は家庭菜園でも栽培が可能です。
特に豆苗は再生栽培ができるため、家庭でもサステナブルな取り組みを実現できます。
1. 再生可能な豆苗の栽培
豆苗は、使用後の根を水に浸けておくだけで、新しい芽が再生します。
再生手順
根の部分を水の入った容器に入れる。
毎日水を交換し、日当たりの良い場所に置く。
1週間ほどで新しい芽が収穫可能。
中国野菜と地産地消
1. 地元産中国野菜のメリット
日本でも多くの中国野菜が生産されています。
地元の農産物を選ぶことで、輸送コストを削減し、フードマイレージを抑えることができます。
2. 有機農法の普及
無農薬で栽培された中国野菜は、環境に優しいだけでなく、安心して食べられるという利点があります。
農薬を使わない農法は、土壌の健康維持にも貢献します。
保存方法、健康効果、環境への配慮といった多方面で魅力がある中国野菜。
これらを日常生活に取り入れることで、美味しく健康的な食生活を楽しむとともに、環境保全にも貢献できます。
これからも中国野菜の魅力をお届けしていきますので、お楽しみに!
以上、第6回野菜の魅力講座でした!
次回の第7回もお楽しみに!
![]()
第5回野菜の魅力講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第5回野菜の魅力講座!
中国野菜の健康効果についてです。
中国野菜には、栄養価が高く健康維持に役立つ成分が多く含まれています。
このシリーズでは、それぞれの野菜が持つ健康効果と、それを活かした食べ方を詳しく解説します。
中国野菜に含まれる栄養素とその効果
1. チンゲンサイ
栄養素
ビタミンC、カルシウム、カリウム
健康効果
美肌効果や骨の健康維持に役立ちます。
特にビタミンCは熱に強いので、炒め物やスープにしても摂取可能です。
2. ターサイ
栄養素
食物繊維、ビタミンA、鉄分
健康効果
腸内環境を整える効果があり、貧血予防にも役立ちます。
濃い緑色の葉は、βカロテンが豊富です。
3. カイラン
栄養素
ビタミンK、カルシウム、鉄分
健康効果
血液の健康を保つと同時に、骨を強化する働きがあります。
4. 豆苗
栄養素
葉酸、ビタミンE、カリウム
健康効果
葉酸は妊娠中の方におすすめの成分で、ビタミンEは抗酸化作用があります。
栄養を活かした健康レシピ
1. 豆苗のスムージー
豆苗とフルーツを組み合わせたスムージーは、朝食や軽食にぴったり。
豆苗特有の風味がバナナやリンゴと合わさることで飲みやすくなります。
2. カイランのサラダ
カイランを軽く茹でて、オリーブオイルとレモン汁でシンプルに味付け。
鉄分やカルシウムがしっかり摂れます。
3. ターサイとトマトのスープ
ターサイの濃い味わいとトマトの酸味が絶妙にマッチ。寒い日に体を温める健康スープとしておすすめです。
以上、第5回野菜の魅力講座でした!
次回の第6回もお楽しみに!
![]()
第4回野菜の魅力講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第4回野菜の魅力講座!
中国野菜の保存方法と栄養を守る工夫についてです。
中国野菜を美味しく食べるには、適切な保存方法が欠かせません。
保存状態が悪いと味や食感が損なわれるだけでなく、せっかくの栄養価も失われてしまうことがあります。
このシリーズでは、冷蔵保存や冷凍保存のテクニック、栄養を守るための調理法をご紹介します。
中国野菜の多くは葉物が中心で、乾燥や湿気に弱いため、保存する際には適切な工夫が必要です。
チンゲンサイやターサイの保存:
湿らせたペーパータオルで包み、ポリ袋またはジップロックに入れて冷蔵庫の野菜室に保存します。
これにより、葉が乾燥せず、2~3日間は新鮮な状態を保つことができます。
カイランの保存:
茎が太いカイランは、茎の部分に湿らせたキッチンペーパーを巻いてから袋に入れると、水分を保ちながら鮮度を維持できます。
特に茎のシャキシャキ感を守るには効果的です。
豆苗の保存:
再生可能な豆苗は、根を水につけた状態で保存するのがおすすめです。
毎日水を交換すれば、数日後にまた新しい芽が伸びてきます。
長期間保存する場合は、冷凍保存がおすすめです。
ただし、冷凍する際には少し手間をかけることで、解凍後も美味しく食べられます。
下茹で冷凍:
1. 野菜を洗い、食べやすい大きさに切ります。
2. 沸騰したお湯で30秒~1分軽く茹でてから冷水にとります。
3. キッチンペーパーで水気をよく拭き取り、ジップロックに入れて冷凍庫へ。
そのまま冷凍:
チンゲンサイやターサイは洗って切った後、冷凍用袋に入れてそのまま冷凍することも可能です。
解凍後はスープや炒め物に使うのがおすすめ。
使い方:
冷凍した野菜は、解凍せずそのまま料理に使用すると食感を損なわずに仕上がります。
炒め物やスープに直接投入するのが最適です。
葉物野菜のビタミンCやカリウムは、加熱すると溶け出しやすい性質があります。
そのため、調理時間を短くすることが栄養を守るポイントです。
炒める場合:強火で短時間で仕上げることで、栄養素をしっかりキープ。
茹でる場合:軽く下茹で程度にし、茹で汁もスープなどに活用すると無駄がありません。
2. 冷凍保存でも栄養を守る
冷凍保存すると一部の栄養が失われると言われますが、正しい方法で冷凍することで栄養価の低下を最小限に抑えられます。
特に葉物野菜は、保存中の乾燥を防ぐことで品質を保てます。
以上、第4回野菜の魅力講座でした!
次回の第5回もお楽しみに!
![]()
第3回野菜の魅力講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
本日は第3回野菜の魅力講座!
中国野菜の調理法とレシピについてです。
簡単で美味しい!中国野菜を楽しむための調理法
初心者でも簡単!中国野菜の基本レシピ
中国野菜はシンプルな調理法でその美味しさを引き出せるのが魅力です。
初心者でも取り入れやすい基本レシピをいくつかご紹介します。
1. チンゲンサイとエビの炒め物
材料(2人分)
チンゲンサイ:2株
エビ:150g
にんにく:1片
オイスターソース:大さじ1
塩、こしょう、サラダ油:適量
作り方:
チンゲンサイを根元から切り分けて洗い、葉と茎を分けておきます。
エビは背ワタを取り除き、塩水で洗ってから下味をつけます。
フライパンにサラダ油を熱し、にんにくを香りが出るまで炒めます。
エビを加えて炒め、火が通ったら一旦取り出します。
チンゲンサイの茎を先に炒め、少ししんなりしたら葉を加えます。
エビを戻し、オイスターソースで味付けし、全体を混ぜ合わせて完成。
2. ターサイのおひたし
シンプルで野菜の甘みを楽しめる一品。冷やしても美味しいです。
材料:
ターサイ:1株
醤油:大さじ1
かつお節:適量
作り方:
ターサイをよく洗い、熱湯で1~2分茹でます。
冷水にさらし、水気を絞ります。
食べやすい大きさに切り、醤油とかつお節をかけて完成。
中国野菜を使った本格レシピ
1. カイランのオイスターソース炒め
中華レストランで定番の一品を家庭でも手軽に再現できます。
材料:
カイラン:2株
オイスターソース:大さじ1.5
にんにく:1片
サラダ油:適量
作り方:
カイランは洗って茎と葉を分けます。茎は縦に薄く切っておくと火が通りやすいです。
フライパンに油を熱し、にんにくを炒めて香りを出します。
茎を先に加え、少し柔らかくなったら葉を加えます。
オイスターソースを絡めて、全体に火が通ったら完成。
2. ターサイと豚肉の鍋
冬にぴったりの鍋料理で、ターサイの濃厚な味を楽しめます。
材料:
ターサイ:1株
豚薄切り肉:150g
だし汁:800ml
醤油、みりん、酒:各大さじ1
作り方:
ターサイを洗い、食べやすい大きさに切ります。
鍋にだし汁を入れ、調味料を加えて煮立てます。
豚肉を加え、色が変わったらターサイを加えて煮込みます。
以上、第3回野菜の魅力講座でした!
次回の第4回もお楽しみに!
![]()
第2回野菜の魅力講座
皆さんこんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
イベント盛り沢山なこの季節、いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は野菜の魅力講座!
今回は、中国野菜の種類についてです。
中国野菜の種類別徹底解説
チンゲン菜:万能で栄養たっぷりな葉物野菜
特徴と栄養
シャキシャキの茎と柔らかい葉が特徴。ビタミンAやカルシウムが豊富で、骨や歯の健康をサポート。
おすすめレシピ
・チンゲン菜の中華炒め
・チンゲン菜と豆腐のスープ
・チンゲン菜とエビのクリーム煮
空芯菜:夏のスタミナ野菜
特徴と栄養
茎が空洞で、シャキシャキとした食感が楽しめる。鉄分とビタミンB群が豊富で、疲労回復に効果的。
おすすめレシピ
・空芯菜のガーリック炒め
・空芯菜と豚肉のさっぱり炒め
・空芯菜と卵の炒め物
ターサイ:冬が旬の葉物野菜
特徴と栄養
見た目がバラのような形状で、甘みが強い。ビタミンKと葉酸が多く含まれ、妊婦さんにもおすすめ。
おすすめレシピ
・ターサイの鍋物
・ターサイと鶏肉の蒸し料理
・ターサイと厚揚げの煮物
ニラ:中華料理の定番野菜
特徴と栄養
強い香りと歯ごたえが特徴。アリシンという成分が疲労回復や免疫力向上に役立つ。
おすすめレシピ
・レバニラ炒め
・ニラ餃子
・ニラのチヂミ
以上、第2回野菜の魅力講座でした!
次回の第3回もお楽しみに!
![]()
第1回野菜の魅力講座
こんにちは!
山村農園、更新担当の那須です。
日に日に寒さが増してくる季節になりましたね。
こんな時こそ、体を温めるスープや鍋物が恋しくなります。
今回は、今注目の!
中国野菜についてご紹介します!
中国野菜は、中国で昔から親しまれてきた、ちょっと個性的でおいしい野菜たちのことです。
中国は気候も土地も広いので、日本では見かけないような野菜がたくさん育てられています。
最近では日本でも栽培が増えてきて、スーパーなどでも手に入りやすくなりました。
普段の食事に取り入れれば、いつものメニューがぐっと新鮮になるかもしれませんよ!
そんな中国野菜には魅力がたくさん!!
料理の幅が広がる!
中国野菜は炒め物、スープ、鍋料理など、どんな調理法にも合います。シャキシャキ感が楽しめるものや、ほのかな香りがクセになるものも多く、「これが中国野菜?」と驚くこと間違いなしです。
栄養たっぷりで健康に良い!
ビタミンやミネラルが豊富で、疲労回復や免疫力アップに役立つ野菜も多いんです。たとえば、チンゲン菜はビタミンAやビタミンCがたっぷり。寒い季節にも体をしっかりサポートしてくれます。
お財布にやさしく手に入る!
最近では、チンゲン菜や空芯菜(くうしんさい)など、気軽に手に取れる中国野菜が増えています。生産が増えているので、スーパーでも手ごろな価格で買えるようになり、手軽に試せるのも魅力です。
日本では、健康志向が高まる中で、中国野菜のように栄養価が高くて調理しやすい野菜が注目されています。
また、見た目も味も少し新鮮なので、食卓に取り入れると家族も「おっ、今日はいつもと違うな!」と感じられるかも。
お手軽に普段の料理に一工夫を加えられる、便利でうれしい存在ですね。
中国野菜は、栄養たっぷりで手軽に使える強い味方!
これからも、もっと身近な存在になることでしょう!
次回!第2回野菜の魅力講座もお楽しみに!!
![]()



